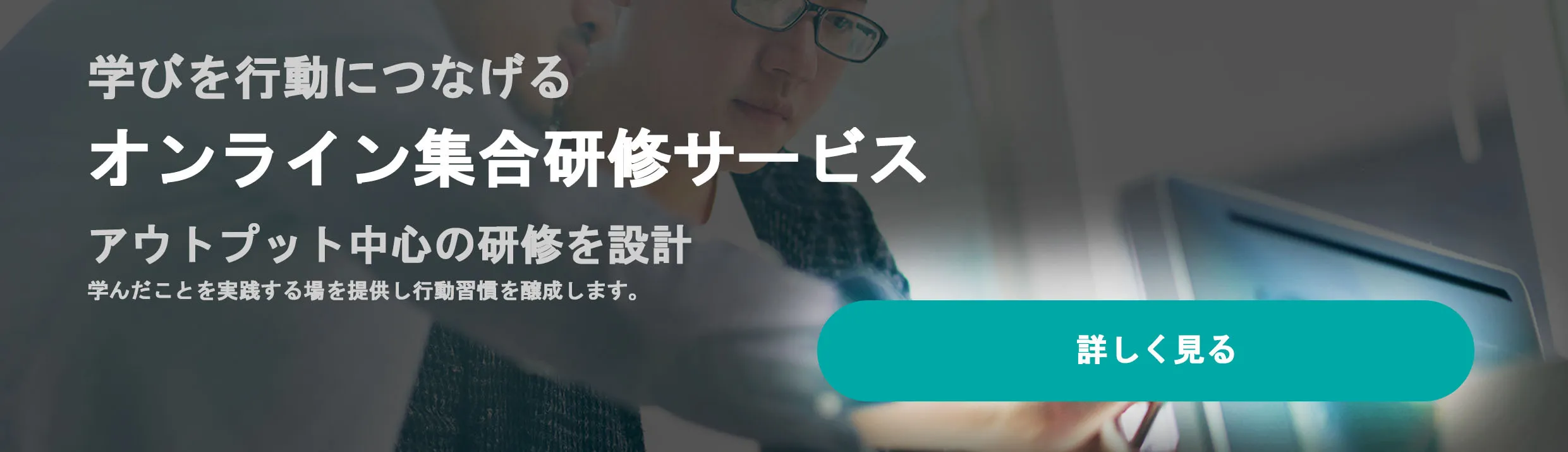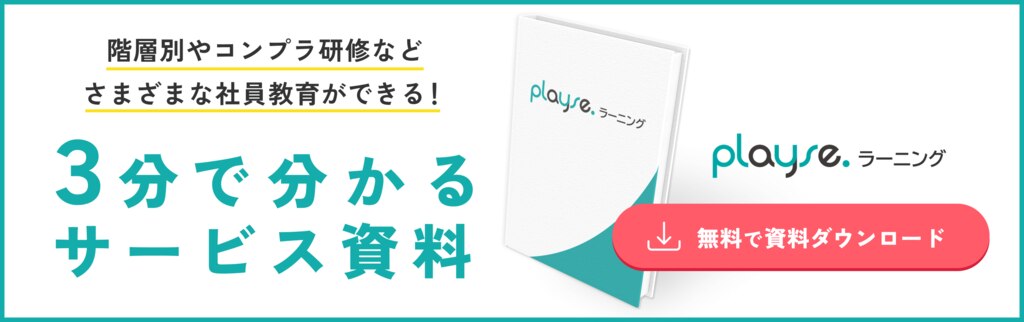コンプライアンス意識を高める研修の具体策を4つのステップで解説!
さまざまなハラスメントや個人情報の管理……。企業のコンプライアンス意識の重要性が叫ばれるなか、その「方法」については曖昧なままになっていることも少なくありません。この記事をご覧になっているあなたは、管理者の立場から「どのように周りに浸透させるべきか」とお悩みなのではないでしょうか。
本記事では、コンプライアンスの意識を高める研修の具体策を 4つのステップをご紹介します。
目次[非表示]
- 1.コンプライアンスとは
- 2.コンプライアンスの意識を高める研修 4つのステップ
- 2.1.【ステップ1】組織をグループに分ける
- 2.1.1.(例)
- 2.2.【ステップ2】「コンプライアンス」の中でも伝えるべきことを絞る
- 2.3.【ステップ3】「くり返し」伝えることで意識を変える
- 2.3.1.具体的な「くり返し」の場
- 2.4.【ステップ4】ケーススタディで「問題発見能力」を養う
- 2.4.1.(例)
- 2.1.【ステップ1】組織をグループに分ける
- 3.ツール・eラーニングを活用し「マンパワー」に頼らない
- 4.おすすめのコンプライアンス研修のeラーニング
コンプライアンスとは
はじめにコンプライアンスの定義を確認しておきましょう。「コンプライアンス」=「法令遵守」と訳されるのが一般的です。しかし「法律を守っていればよい」という意識では危険が伴う場合もあります。法律だけでなく、企業倫理としてマナー・社会ルールを守ることも求められているのが現状だといえるからです。
社員のコンプライアンス違反によって、会社そのものが倒産の危機に直面。そんな事例も珍しくありません。「知らなかった」では済まされなくなっているのが、現在の企業に対する見られ方なのです。
コンプライアンスの意識を高める研修 4つのステップ

それでは、会社全体にコンプライアンス意識を浸透させる4つのステップを紹介します。
【ステップ1】組織をグループにわける
まずあなたの会社の組織をイメージしてみてください。ある程度キャリアを積んだ中堅社員がいれば、社会に出て間もない新入社員や学生アルバイトもいるかもしれません。すると、社会人経験によって彼らの「当たり前」の意識に差があると予想できます。
前提知識が異なるメンバーに一斉に同じことを伝えても、難しすぎたり不要な内容が含まれていたりして「当事者意識」を持たせづらくなってしまいます。一律で教育をするのではなく「メンバー」をさらにグループにわけて、それぞれに適した研修を行うことが重要です。
(例)
- 管理職…組織全体が常にコンプライアンス意識を持って機能するためのマネジメント方法
- 中堅社員…コンプライアンスの具体的な事例の共有・部下への教育方法
- 新入社員・アルバイト…自分の業務に直接かかわる基本的な内容の周知・意識づけ
グループわけをしたら、経験値の高いメンバーから教育を始めます。先に自分の「仲間」を作り、協力してもらいながら全体へ浸透させる流れで研修を進めていくと効率がよいでしょう。
【ステップ2】「コンプライアンス」のなかでも伝えるべきことを絞る
はじめに、コンプライアンス教育には、法律以外にもモラルやマナーの意識づけも含まれるとお伝えしました。そのため範囲がとても広く、全てを伝えようとすると大変な労力となり現実的ではありません。
あなたの組織やメンバーに必要な知識はどこまででしょうか。不正会計(粉飾決算、脱税)や独占禁止法違反? それとも、まずは個人情報の徹底管理やパワハラ・セクハラなど業務に身近なところから……?研修を始める前に、必要なのはどのレベルまでなのかを洗い出すことが、無駄なく的確な教育への近道です。
- 組織のグループわけ
- 各グループに必要な知識の洗い出し
- 洗い出した知識の優先順位付け
- 各知識の研修内容の決定
このように順序立てて研修を組んでいくと、内容が整理されてつながりのある内容になっていきます。
【ステップ3】「くり返し」伝えることで意識を変える
伝えるべき範囲が決まったら、次はその方法。ポイントは、会議や研修の場で「くり返し伝える」ことです。何度も話題に出すことが「重要度」を表すメッセージとなります。
学生時代を思い出してみてください。テストに出そうな重要範囲は、先生が何度も強調してくれていませんでしたか? そして生徒である私たちは「あっ、これは覚えておかないと!」と強く意識しましたね。それとまったく同じです。大きな研修で一度きり……よりも、「くり返し」が効果を発揮します。
具体的な「くり返し」の場
- 新入社員研修時
- 昇格・異動時の面談
- 日々の会議・ミーティング・朝礼の冒頭(社内での事例やニュースになったコンプライアンス違反などを取り上げるのも可)
- 日々の何気ない会話
- 定期的にメールで注意喚起
日常業務のなかに意図的に「くり返し」の場を作るほど「今、自分の会社(上司)はコンプライアンス教育に力をかけている」と強烈に意識づけるメッセージになります。
【ステップ4】ケーススタディで「問題発見能力」を養う
コンプライアンス教育のカギは、いかに「当事者意識」を持たせられるか。たんに指示や研修での話を聞いているだけでは受け身の姿勢となって、「自分のこと」として捉えにくいものです。コンプライアンス教育に時間やコストをかけつつもなかなか浸透しないときには、この「アウトプット」が欠けていた……というケースもよくあります。それでは投資に見合わないですよね。
そんなときはケーススタディを活用し、「この場合何が問題となりそうか?」「自分ならどんな解決策を出すか?」などをレポートや発言からアウトプットさせるとよいでしょう。より少人数のグループに分けて実施すると、発言の機会も増え、社員の自発的なアクションやコンプライアンス意識の高まりが期待できます。
(例)
- パワハラに関する具体的な事例を紙ベースで示し、グループごとに「解決策」をディスカッションさせる
- 架空の社内映像を見せ、「どの部分に問題が起こるリスクがあるか」を見つけさせる
\社内でコンプライアンス意識を高めるためのポイントが一冊に/

ツール・eラーニングを活用し「マンパワー」に頼らない

研修や教育は「継続的な実施」が非常に重要です。
- それぞれの立場の社員に合わせた内容
- 最新のコンプライアンス情報にアップデートした内容
- 「くり返し」学べる環境
上記を満たし続ければ社内でのコンプライアンス意識は強まっていくでしょう。しかし、これらを全てマンパワーで補おうとすると、人的負担が大きくなりすぎるもの。はじめは勢いよくやっていても気づいたらおざなりになってしまう可能性も高いです。
「知識だけを一律に伝える」「復習として同じ内容を伝える」など、「人」が直接行う必要がないものについては、eラーニングを活用するとよいでしょう。反対にケーススタディといったアクティブな研修は「人」が熱量をかけていくと、想いの伝わる研修になります。
コンプライアンス研修としてオススメ!「playse. ラーニング」
コンプライアンスに対する意識を高めるため、研修内容・場所の確保・管理やチェックなどの仕組みづくりをゼロから積み上げていくと、多くの手間と時間がかかります。
「playse. ラーニング」なら、リソースに余裕がなくても、労力や時間コストを抑えつつ質の高いコンプライアンス研修をオンラインで行えるのでオススメです。
「playse. ラーニング」は、ハラスメント関連のコンテンツを含む約5,000レッスンが見放題のeラーニングシステム。スマートフォンやパソコンからいつでもどこでも学習でき、テスト・アンケート機能つきなので、理解度チェックも可能です。
詳しいサービス資料やオンライン研修、eラーニングシステムの活用に関するご相談など、お気軽にお問い合わせください。