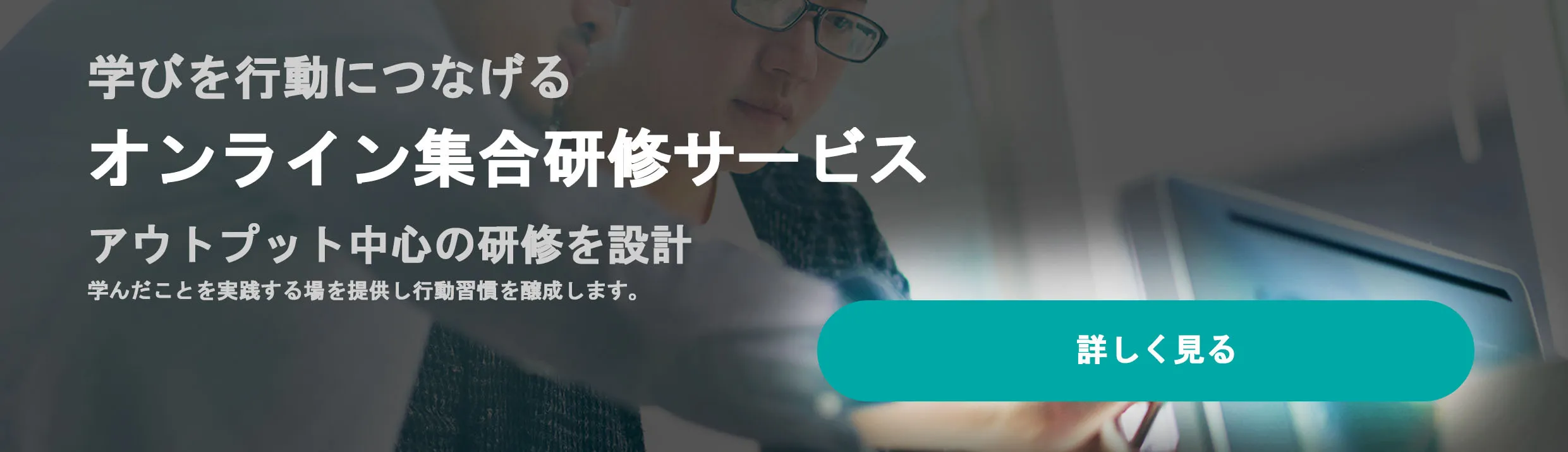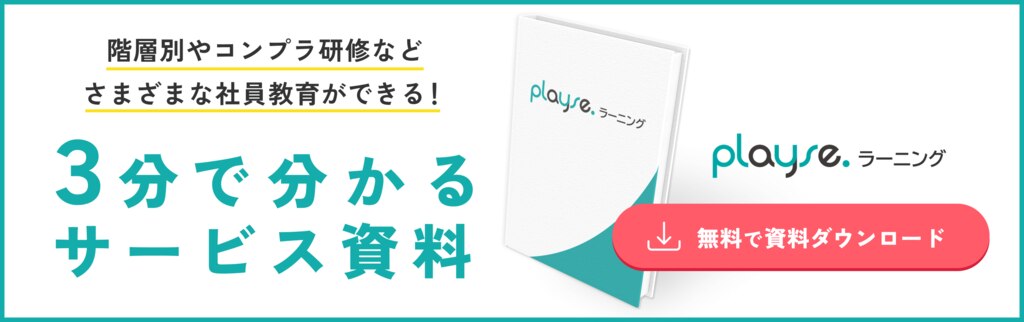新入社員研修がきついと感じる理由とは?起こり得るリスクや対策・ポイントを解説
新入社員研修に参加した新入社員のなかには、「きつい」と思っている人や、強い不安を感じている人がいます。こうした新入社員は必要なスキルが身につきにくいため、配属後の教育に影響が出たり、早期離職につながったりするかもしれません。本記事では主に人事担当者に向けて、新入社員研修がきついと感じる理由と対策を解説します。
- 新入社員研修がきつい感じる7つの理由
- きつい新入社員研修が引き起こすリスク
- きついと感じさせないためのポイント、具体策
- きついと訴えられた場合の対処方法
1.新入社員研修がきついと感じる7つの理由

新入社員研修中に体調を崩してしまう人や、強いストレスを感じている人は少なくありません。なぜ新入社員は研修を「きつい」と思うのでしょうか。代表的な理由を7つ紹介します。
1.会社や環境の変化に慣れていない
一般的に新入社員研修は入社直後の4月からはじまり、平均的には1か月〜3か月程度実施されます。新入社員は学生時代と違って自由が利かない環境や、慣れないビジネスマナーを使うことなどにストレスを感じがちです。また職場以外でも、早起きや通勤ラッシュなどで体調を崩しやすい傾向があります。
環境変化への適応には個人差があるため、適応力の強い人を基準にスケジュールや研修内容を組んでしまうと、脱落者が増えるリスクが高いです。とくに多数の新卒を受け入れる際は、集団をひとくくりに考えてしまい、個人を軽視してしまいやすいので注意しましょう。
2.覚えるべき情報量が多い
新入社員が研修で覚えるべき内容は多岐にわたります。主な内容は以下のとおりです。
- 会社の経営理念や事業活動の理解
- ビジネスマナー
- コミュニケーションスキル
- マインドセット(積極性、協調性、顧客視点などについて)
- パソコンやオフィス設備などの理解
また、職種別の研修もあります。たとえば、企画職なら顧客理解やマーケティング知識、企画書作成スキルなどのように、その分野の基礎知識を習得しなければなりません。このように、新入社員研修は短期間で多くの内容を詰め込む形になっています。「強い緊張感や不安を感じたり、気持ちが落ち込んでしまったりする新入社員がいても無理はない」と考えられる指導者としての姿勢が大切です。
3.指導者が厳しい
新入社員研修では、社会人として責任ある行動ができるよう、あえて厳しく指導するケースがあります。ねらいとして挙げられるのは「社会人としてのスイッチを入れて短期間で即戦力化させる」「組織のルールに従うことを学ばせる」などです。
極端な例では、滝行や登山などをさせてストレス耐性を鍛えたり、大声で声出しをさせて羞恥心を捨てさせようとしたりする会社もあります。こうした研修では、人としての尊厳を傷つけられたと感じる人や、「ひどい会社に入ってしまった」と激しく後悔する新入社員がいても不思議ではありません。
そのほか、意図的に厳しくしようとしなくても、指導者が新入社員につらくあたってしまうケースもあります。よくあるのは、社員が本業の合間に研修をしており、気持ちや時間に余裕がないケースです。また、研修スキルがないため、的確にアドバイスしたり、やる気を高める声がけができなかったりするケースもあります。
4.人間関係が上手く構築できない
指導担当者との人間関係に悩む人もいます。指導担当者と新入社員の間には、知識・経験・スキルで大きな差があるため、人間的な親しみを感じられない場合もあるでしょう。また年齢差があって、世代間ギャップを感じる人も少なくありません。とくに指導が厳しければ、教える立場・教わる立場という上下関係が強くなり、心をオープンにできないケースも多いでしょう。
また、Z世代以降は個性を生かすことを大切にする教育で育っており、教えたとおり実行するように促す研修方法に、苦手意識を持つ新入社員も増えているようです。したがって、近年ではコミュニケーションスキルの高い外部機関の講師に研修を任せる会社や、指導担当者が積極的にフラットなコミュニケーションを心がける会社も多くあります。
5.研修期間中の行動制限が起こりやすい
新入社員研修中に、鳥かごに入れられたような閉塞感、圧迫感を持つ新入社員もたくさんいます。会社によって研修方法は異なるものの、大きな会議室に缶詰め状態にして集中的に研修を受けさせたり、ホテルや合宿所などに泊まり込みで研修を受けさせたりするケースが多いためです。
「自分が自由に過ごせる時間」「ひとりになれる時間」を大切にする新入社員にとって、行動制限をかけられるのは大きな苦痛になります。とくに組織のなかで自分の考えや意見を安心して発言できる「心理的安全性」がない環境下では、ストレスがさらに強くなるでしょう。
6.監視されていると感じて緊張状態が続く
先ほどの閉塞感、圧迫感を身体的なストレスとすると、精神的なストレスの原因になりやすい点に「つねに監視されている」という意識が挙げられます。自分の様子が逐一観察されており、採点されているように感じるからです。このストレスが強くなりがちな研修としては、指導担当者のほかに上司や先輩などが同席しているケースが挙げられます。何か行動するたびに間違いを指摘されたり、こうしたほうがよいとアドバイスされたりすれば、ストレスがたまってしまうでしょう。
また、人事担当者が様子を観察し、人材配置の参考にしている場合も無言のプレッシャーを与えます。希望の配属先がある人や向上心が高い人ほど、自分を追い込んでしまう可能性が高いため注意が必要です。
7.研修内容に納得できない
新入社員研修に意味や価値を見いだせない人もいます。たとえば、研修で学ぶ知識やスキルが実務に必要だとわかっていても、どうやって生かせばよいのか具体的にイメージできないケースです。また、「スキルアップや人間的な成長につながらない」と思いながら研修を受けている人もいます。
研修に納得感がない理由として多いのは、「なぜこの研修が必要なのか」を丁寧に説明していないケースです。たとえば、挨拶指導のときに、「挨拶はビジネスの基本」という常識で片づけてしまい、具体的な理由を説明していない場合があります。一般社員にとって当たり前のことでも新入社員にとっては理由がわからない事柄は多いため、丁寧な説明が求められるのです。
2.新入社員研修がきついことで起こり得るリスク

新入社員が研修に対して悪い印象を持ってしまうと、どのような問題が生じるのでしょうか。大きな問題に発展してしまうケースもあるため、リスクについて知っておきましょう。
不安を抱えたまま新入社員が配属される
新入社員研修をきついと感じている新入社員のなかには、学ぶべき業務知識やスキルを身につけられていない人が少なくありません。したがって、配属後にミスを重ねてしまう場合や、不安が大きいため自主的に行動できない場合もあります。手厚いサポートが必要となるため、ほかの社員の負担も大きくなってしまうでしょう。
長期的にみると、さらに大きな影響が考えられます。研修での挫折をきっかけに、仕事に対するモチベーションや自信を失ってしまえば、その後の成長が遅れてしまうでしょう。最悪の場合、戦力化できないケースも考えられます。また、職場の生産性が低下したり、コミュニケーションが円滑に回らなくなったりするなど、周りに影響がおよぶ可能性も高いです。
離職率が高くなる
新入社員研修中に「きつい」「入社する会社を間違えた」などと感じた新入社員は、早期退職を考える可能性が高まります。研修中に辞めてしまうケースは稀です。一方、出だしで働く意欲がそがれてしまえば、配属後も仕事にやりがいを持てず、辞めてしまうリスクが高まってしまいます。
厚生労働省の発表によれば、2019年3月に卒業して就職した学生のうち3年以内に離職する割合は、新規高卒就職者の35.9%、新規大卒就職者の31.5%。会社が優秀な人材を早期離職で失うリスクは、依然として高い状況といえるでしょう。何事もはじめが肝心ですので、新入社員研修でつまずかない対策を用意しておきたいところです。
参考:新規学卒就職者の離職状況(平成31年3月卒業者)を公表します|厚生労働省
今後の採用活動に悪い影響が出る
新入社員が、研修できつかった経験を学校の後輩や友人などに話す可能性が考えられます。このような場合、悪い面が誇張されて伝えられやすいため、噂が広まると、採用活動に悪い影響が出るかもしれません。例年、同じ学校から新卒採用しているような会社は、とくに注意するべきといえるでしょう。
また、SNSや転職サイトの口コミ欄などで、新入社員研修への不満を伝えるかもしれません。実際パワーハラスメントやモラルハラスメントなどの事実が流出してSNSで炎上し、採用活動に支障が出てしまった事例もあります。インターネットでは情報拡散が早く、炎上の可能性も高まっていますので、十分な注意が必要です。
3.新入社員研修をきついと感じさせないためのポイント

新入社員研修を企画する人事担当者としては、なるべく新入社員にやりがいを持って取り組んでもらいたいもの。ここでは具体的な施策の紹介に移る前に、新入社員にきついと感じられにくい研修にするための基本方針を解説します。
スケジュールやプログラムに余裕を持たせる
新入社員研修のスケジュールやプログラムには、ある程度の余裕を持たせておくことが大切です。優秀な人やストレス耐性が強い人に合わせて研修を企画すると、途中で挫折してしまう新入社員が増えるリスクがあります。必ず確保しておきたいのが休憩時間です。会社では学校のように休憩時間がないため、指導者の裁量に任せると、長時間続く研修になってしまうおそれもあります。
少なくとも90分に1回は10分程度の休憩を入れましょう。人間の集中力は90分程度しか続かないといわれているため、適度な休憩によって能率が上がると期待できます。時間がどうしても足りない場合、そもそものスケジュールに無理があるのかもしれません。
近年はeラーニングを用いて新入社員に自発的に学習してもらったり、配属後に研修を続けたりする方法もあります。対面研修にこだわらず、ゆとりを作り出してみてはいかがでしょうか。
研修内容にチームワークを取り入れる
新入社員研修には、個人ワークだけでなくチームワーク(複数人で協力、連携しながら取り組む共同作業)も取り入れるとよいでしょう。新入社員同士の人間関係が築かれやすくなります。また、一人で悩みを抱え込まず、相談し合うようになる効果も期待できるでしょう。
チームワークは「企画を考えて発表する」といったアウトプットが中心です。このため、座学のようなインプットと違って、やりがいや達成感を得やすくなります。研修を通じて自身の成長を感じてもらう機会にできるでしょう。ただし、チームワークは時間配分がむずかしく、個人の達成度が把握しづらい面もあります。作業内容とボリュームを慎重に決めることが必要です。
新入社員研修の目的・メリットを伝える
先にも述べたように、新入社員研修がきついと感じる理由として、研修の目的や意義、得られるメリットがわからないことが挙げられます。新入社員にモチベーションを持って取り組んでもらうためにも「なぜ研修に参加しているのか」「なぜこの内容を学ぶのか」などをしっかり伝えることが大切です。
たとえば、新入社員研修の全体的な流れを説明したうえで、研修終了後にどのような人間になってもらいたいか伝える方法があります。具体的なイメージを持ってもらえるよう、年次や職種などが近い人をロールモデルにして伝えるとよいでしょう。
また、自分で目標やゴールを考えてもらう方法もあります。自主性を刺激することで、新入社員研修にありがちな押しつけ感や束縛感が薄れるからです。また、「つらい=成長へのチャレンジ」のように、ポジティブにとらえてもらう効果も期待できます。
4.新入社員研修をきついと感じさせないための対策

ここまで新入社員にきついと感じさせないための研修の基本方針を紹介してきました。ここからは、具体的な施策をみていきましょう。どの施策が優れているというわけではなく、自社に合った施策を選ぶことが重要です。
メンター制度を導入する
メンター制度とは、先輩社員が新入社員や後輩の指導・助言役(メンター)となってサポートする制度です。運用の仕方は会社によって多少違います。一方、主な特徴は以下のとおりです。
- 業務だけでなく、人間関係の悩みなど精神的な面も含めてサポートする
- 年齢や勤続年数があまり離れていない先輩社員を選ぶ
- 他部署の先輩社員をメンターにすることもある(率直な意見を言える環境を整えるため)
メンター制度は、新入社員研修の指導担当者がサポートしにくい部分をカバーし、問題を早期発見できるのがメリット。メンターは指導担当者より距離感が近いため、相談しやすい面があります。また、面談などで研修内容を補足する時間を設ければ、研修スケジュールや内容に余裕が生まれるでしょう。
配属先の上司との面談を実施する
新入社員研修後の配属先が決まっている場合、直属の上司になる人との面談を設けるのも効果的です。新入社員研修でがんばっていることを評価したうえで、研修が実務にどのように役に立つのか伝えることが目的といえます。また、配属先部署でどのような人材が求められているのかを伝えて、新入社員の課題意識をはっきりさせることも対策のひとつです。
つまり、面談は新入社員研修の一環として考えます。上司は「新入社員が仕事で認められるイメージを持てる」「モチベーションを持って研修を受けられる」よう面談しましょう。逆に、上司が配属後に必要な知識やスキルなどを教えようとしてしまう点には注意が必要といえます。なぜならただでさえ覚えるべき情報量が多い研修の負担をさらに増やすことになるからです。
メンタル面をサポートできる体制を整える
メンタル面のサポートを手厚く実施する体制を整えておくことも大切です。「眠れない、気持ちが落ち込むなどのメンタル不調はないか」「ストレスによる体調不良がないか」などをヒアリングして、一緒に解決していく体制を整えます。
方法のひとつは、人事担当者が相談役になること。この場合、人事担当者が指導担当者を兼任するのはむずかしいため、すべてを人事担当者に委ねず、外部機関に研修を任せましょう。人事担当者は新入社員の側に立ってフォローに徹すると効果的です。
しかし、メンタル面のサポートはデリケートな部分も多いため、産業医や保健師など、専門的な知識を持った人に頼むのも視野に入れましょう。この場合、産業保健スタッフと協力して、相談窓口を設けてもらったり、面談の機会を作ったりするなど体制を整えます。
グループワークを研修プログラムに取り入れる
グループワークとは、5人程度のグループを作り、与えられた課題について議論を交わしながら、チームとして最終的な結論や成果物を発表する作業のこと。コミュニケーションやチームワークを学べるグループワークは、社内研修でよく用いられています。グループワークが新入社員のストレスや不安を緩和しやすいのは、同期と交流する場を与えられるためです。共通の課題を解決するプロセスを通じて仲間意識が芽生えやすくなります。
また、参加意識やモチベーションを高めやすいのもグループワークのメリット。グループワークは自主性や創造性を刺激するアプトプット型研修ですので、知識を覚えさせる座学と対照的といえるでしょう。たとえば「当社の新規事業を考案してください」「ただの石を1万円で売る方法を考えてください」のように、正解がないテーマを選びます。覚えたり学んだりする意識から解放されるため、新入社員にとってよい気分転換になるでしょう。
外部によるビジネスマナー研修を取り入れる
外部から講師を招いて質の高い研修を実施するのも有効な対策のひとつ。たとえば、ビジネスマナーを教える専門講師を招けば、座学や実習などでメリハリを付けながら、短期間で効率的に教えてもらえます。結果として、新入社員は興味や納得感を持って課題に取り組め、ストレスを感じにくくなるでしょう。
外部講師による研修を取り入れると、社内の負担が減り、自社社員にしかできない内容に注力できます。たとえば、経営者やマーケター、エンジニアのように各部門の人材を呼んで得意分野を講義してもらうなど、研修にバリエーションを持たせられるようになるでしょう。
現在はe-ラーニングを取り入れる企業も増えてきました。「playse.ラーニング」は、オンラインで教育ができるラーニングプラットフォームです。豊富なジャンルのなかから目的に合ったカリキュラムを組み合わせて、任意のスケジュールで研修を受けてもらえます。また、オンライン上で個々の学習状況も確認可能です。
5.新入社員研修がきついと訴えられた場合の対処方法

新入社員から研修が「きつい」「厳しすぎる」などの声が出た場合、人事部門はどう対処すればよいのでしょうか。緊急を要するケースもあるため、まずは相手の立場になって状況を確認するとよいでしょう。ここでは対処方法をふたつ紹介します。
研修スケジュール・内容を見直す
たくさんの新入社員から「研修についていけない」という声が出た際は、スケジュールや内容に無理がある可能性があります。予備日を設けている場合、スケジュールを調整して新入社員の負担を減らすとよいでしょう。予備日がなく配属予定日を延長する際は、関係各所との調整が必要です。ただ現実的にはむずかしいケースも多いため、優先度が低いカリキュラムの削除も検討することになるでしょう。
カリキュラムを減らしたくない場合には、先ほど紹介したe-ラーニングによる対応が有効です。たとえば「任意でスキルを伸ばしてもらいたい内容は、時間があるときにe-ラーリングに取り組んでもらう」といった、柔軟な対応が可能になります。
場合によっては研修への参加を中断する
体調面や精神面に不調が出てしまっている場合は、研修への参加を止めさせる判断をします。社員の健康と安全を守るのは会社の義務ですので、無理をさせて状態が悪化する事態は避けなければなりません。ただし、人事部や指導担当者などが判断するのは、むずかしい面もあります。医学やメンタルヘルスの知識を持った産業医や保健師など、専門家の意見も聞きながら対応するとよいでしょう。
なお、新入社員研修中に体調を崩してしまう人は少なくありません。この際、誰にどうやって連絡したらよいか悩む人が多くいます。研修開始時に連絡先や相談方法をしっかり伝えておきましょう。
6.新入社員研修の「きつい」を「成長」に変える対策が必要

新入社員を教育するために、新入社員研修はなくてはならないものです。ときには厳しい指導をしたり、負担の大きい課題に取り組んでもらったりする場合もあるでしょう。新入社員を適切にサポートしながら、成長につなげていくことが大切です。質の高い新入社員研修にしていくには、外部機関の講師やカリキュラムを活用するのもひとつ。「playse.ラーニング」では、新入社員向けの研修コースを低価格で提供しています。インターネット環境があれば特別なツールは不要ですので、導入もスムーズです。
また、カリキュラムの策定が大変という人事担当者の方に向けて、カリキュラム作成のサポートもしていますので、ぜひご活用ください。資料請求は「playse.ラーニング」サービス資料・教材一覧ダウンロードから。
お役立ち資料
【パワハラ防止法とは?パワハラの定義と企業が行うべき対策を解説!】
【コンプライアンス意識を高めるためのポイント〜研修の定着率も考える〜】