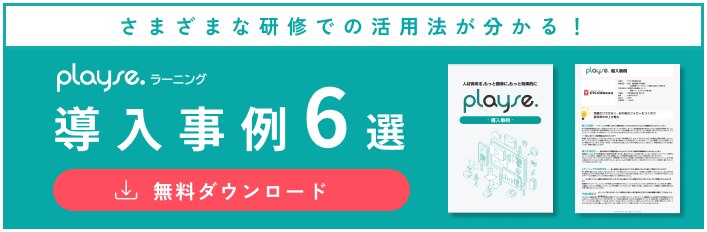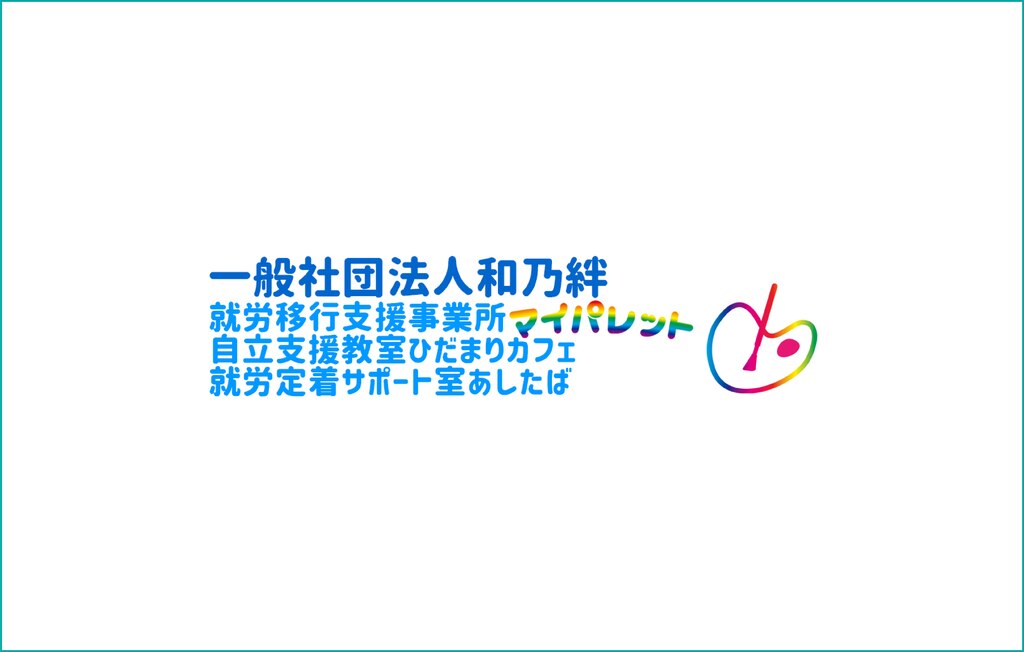
事業内容:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業、上記に掲げる事業に附帯または関連する事業
所在地:和歌山県和歌山市毛見1130-1 T.Tビル1F
理事長:田中 忍
設立:平成26年11月4日
従業員数:7名
URL:https://wanokizuna.org/index.html
■お話をお伺いした方
安藤様
導入の背景
── どのようなきっかけでeラーニングシステムの導入を検討されたのですか?
元々学習プログラム自体はありましたが、誰がどこまで受講したのか、どの授業に参加したのか欠席したのか、受講者の管理がしきれていなかったんです。そんな時に緊急事態宣言が発令されて、対面での業務が難しくなったこともあって、eラーニングシステムを探していました。対面の業務が難しくなったとは言っても、支援を途切らせてはいけないと思っていました。
導入の決め手
── 数あるeラーニングの中でplayse.をお選びいただいた理由は何だったのでしょうか?
障害福祉の就労支援に特化した他社のeラーニングシステムをデモ利用していたのですが、自社コンテンツのアップロード機能がないことや、コンテンツ数も20程度と少なく、且つ受講できる順番が固定されていてコンテンツをスキップして受講するといった自由がきかないため、導入を見送りました。playse.は自作のコンテンツもあげられるのが良いと思います。また、利用者さんが就職する業界も様々なので、搭載されているコンテンツの幅が広いのも良かったですね。
eラーニングの活用方法
── 今はどのようにeラーニングシステムを利用されていらっしゃいますか?
色々な支援をする中で、隙間時間をつかってeラーニングを受講してもらっています。まずは、システムにログインできた、自分も普通の企業で働くことができるかもしれないと感じてもらえるようにしたいです。
── 小さな成功を体験してもらうことはとても良いですね。1日のどこかに10分でもeラーニングを触る時間を継続的に作っていただくと、操作に慣れて習慣的にシステムを使ってもらいやすくなると思います。
そうですね、システムに慣れさせるという観点がなかったのでぜひ取り組んでみたいと思います。
── システムにアップロードする自社教材はスタッフの皆様が作成していらっしゃいますか?
いえ、各企業様や団体が福祉サービス用に提供してくださっているコンテンツを利用させてもらっていますが、細かいところは自分たちで修正して利用しています。
── 就労支援をする中で感じる教育の課題はありますか?eラーニングの導入で実現したいことをお聞かせいただきたいです。
利用者さんの就職は、自分で希望した仕事に就くというよりも、どんな求人があって、どんな仕事をさせてもらえるのかというところからスタートするので、基本的に受け身になってしまっているのが現状です。普通の方のように、興味のあるコンテンツを自分から観るというのもなかなか難しいのが課題ですね。それを自分からできるようになったらすごいことだと思います。
それから、実際に就職が決まって現場に行っても、突然自分の知らない世界に入っていくことになるので、平常心でいられなくなって研修の内容も頭に入らず、汗びっしょりになって帰ってきたりします。私たちには「何もわからなかった…」と報告できるけれど、その場でわからないことを表明することが怖いという状況です。製造現場やコールセンターなど、自分がイメージしているものと現状が違った場合、往々にしてそのようなことになってしまいます。でも、現場の指導者からは、特に問題なかったと報告を受けることもあるので、その時は「実はこうなんです」と間に入ってフォローすることも多々あります。
── そうなんですね。就職先の職場風景や仕事の様子を撮影した動画をシステムにアップロードして、事前に観てもらうことでイメージを持ってもらえるようにするといいかもしれませんね。
そうですね。そのような動画を撮影できたらとても良いと思います。今度企業に働きかけてみます。
eラーニング導入の効果
── eラーニングを導入してから、やりやすくなったことや改善したことはありますか?
支援する内容によって多くの人が携わるので、私は良いと思うけど他の人は良いと思わないなど、教育プログラムをまとめることが難しい状況だったのですが、eラーニングシステムを導入して教育内容をまとめることができました。あとは、現時点で目に見えて効果が出ているのが、職員の教育ツールの管理です。紙の教材をデジタル化してシステムにアップロードしたので、教材を探す手間が大幅に削減されました。
── 御社はかなりシステムを使い熟していらっしゃる印象がありますが、こうしたシステム運用が得意なスタッフ様が多いのでしょうか?
いえ、平均年齢が50歳でシステムに詳しい者は特にいないので、私が一人で設定しています。空いている穴があったら埋めたくなる性格なので、一つずつ機能を確認して使っているだけです。(笑)
今後の展望
── 今後eラーニングシステムを活用して取り組んでいきたいことはありますか?
現在は、施設内で職員が受講者にeラーニングのコンテンツを見せている状態なので、これを個々人が自宅でログインしてコンテンツを視聴するという状態まで持っていくのが次の課題です。付きっきりの対面支援は負担が大きいので、オンラインで支援できるようにするためにはどのようにしたらいいかを考えています。特に難病の方の支援は必ず現場まで行かなければならず、ヘルパーさんとの調整も必要なので課題は多いです。
ゆくゆくは当施設の利用者以外にも、このような学習支援を展開していきたいと思っています。当施設は行政に認められた方でないと利用ができないため、グレーゾーンの方に対しての支援ができない環境です。私たちは非営利団体なので、それをどのようにしていけばよいかを考えているところです。
── その取り組みはぜひご支援させていただきたいです。本日は色々とお話しいただきありがとうございました!
関連記事

ネグロス電工株式会社様
全従業員が「自ら学び直す環境」を構築。自社の内製コンテンツも活用

小泉機器工業株式会社様
入社前の研修と自由受講で活用、学習を実務に生かした事例も

悠悠ホーム株式会社様
職種別ロードマップでキャリアの道筋を明確化!学びのカルチャー創出への挑戦

フォションホテル京都様
ホテル従業員から好意的な声。学習意欲の向上や自主的な学習行動も増加

株式会社ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング様
必須研修と自由受講を実施、スムーズなアカウント管理による工数削減を実現

株式会社いつも様
運営作業時間の大幅削減に成功、コンプライアンス研修と社内ナレッジの一元管理に活用
CONTACT
お問い合わせ
©manebi inc. All rights reserved.