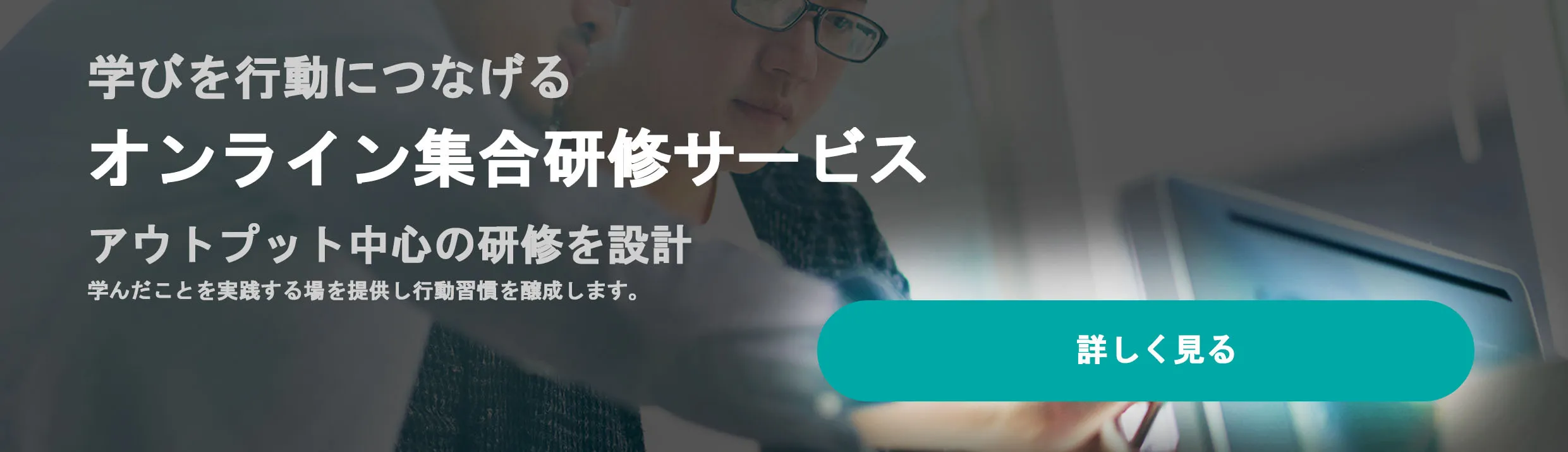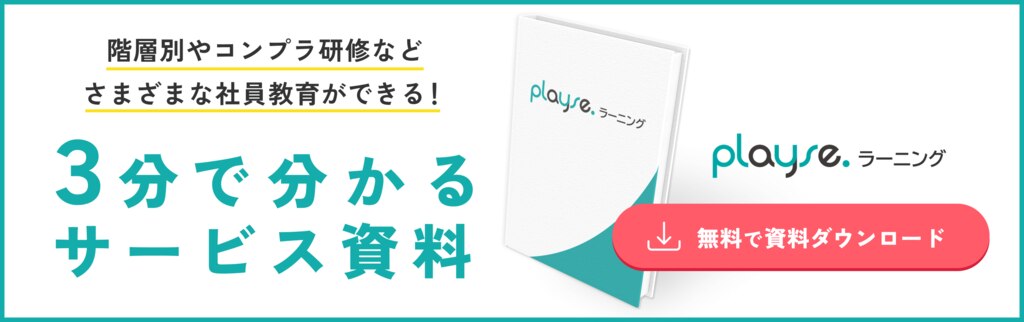社員教育に効果的な反転学習とは?メリット・デメリットとやり方を解説
企業価値の向上や生産性アップのため、多くの企業が社員教育に注力しています。しかし、企業側がいくら研修をとおして必要な知識を提供しても、思うように教育効果が得られない場合もあるでしょう。そこには「教育の方法が適切でない可能性」が隠れているかもしれません。
もし現在の社員教育の効果に満足していないのであれば、「反転学習」がオススメです。今回は、反転学習の概要や効果、メリット・デメリット、やり方やポイントなどを解説します。
目次[非表示]
- 1.反転学習とは
- 1.1.反転学習の効果
- 1.2.反転学習は社員教育に最適
- 2.反転学習のメリット
- 2.1.自分のペースで繰り返し理解を深められる
- 2.2.能動的なアウトプットの機会が増える
- 2.3.管理者が進捗を管理しやすくなる
- 3.反転学習のデメリット
- 3.1.事前学習をこなす必要がある
- 3.2.事前学習の教材を用意する手間がある
- 4.反転学習のやり方
- 5.反転学習のポイント
- 5.1.事前課題でレポートやテストを提出させる
- 5.2.事前課題に取り組みやすい環境を整える
- 5.3.研修後の目標を明確にする
- 6.反転学習に使えるおすすめツール「playse. eラーニング」
反転学習とは
反転学習とは、学習者に事前に学習してもらってから、講師による研修を実施していく学習方法のこと。一般的な研修では、講師が新しい知識を教えたあと、学習者が自宅で課題をこなして知識を身につけていく学習方法を採用しています。
反転学習ではこの流れを反転させ、学習者にWeb上などで事前学習をこなしてもらってから、講師による研修を実施していくのです。つまり、通常は「授業→復習」の流れで進める学習を、「予習→授業」の流れで進めるといった形になります。
反転学習の効果
反転学習をすると、学習者は必要な知識を身につけてから研修を受けられます。そのため研修では単なる座学だけではなく、グループワークやロールプレイングなどを通じた、より実践的な学習を受けられるのです。
反転学習は社員教育に最適
従来の教育法では、社員によって知識のばらつきがあったり、学習後の習熟度に大きな差が生じたりしやすい傾向にありました。しかし、反転学習では事前学習で社員の知識を均一化できるため、習熟度に差が生まれることを防げます。
さらに事前知識があるからこそ、講義ではなく実践的な教育に時間を割けるようになり、即戦力となる社員を育成可能です。人材不足が深刻化する日本の教育シーンには、効率よく即戦力になる社員を育成できる反転学習が最適といえるでしょう。
反転学習のメリット
より反転学習について知るために、ここからはそのメリットについて見ていきましょう。
自分のペースで繰り返し理解を深められる
反転学習を行う際は、事前にeラーニングといった教材を利用し、研修の基本知識を身につけていきます。この段階である程度の情報を学んで自分に落とし込めるため、後に行う研修をスムーズに習得できる準備が整えられるのです。
また自分のペースで何度も学べるため、従来の教育法のように聞き逃したりついていけなくなったりするのも防げます。必要に応じて教材の反復学習や早送りができるので、効率よく知識を深められるでしょう。
能動的なアウトプットの機会が増える
あらかじめ基礎知識を学ぶ反転学習では、実際の研修で講義を行う必要がありません。最低限の説明をしたあとは、ロールプレイングなどによる実践形式のカリキュラムや、学習者の質疑応答に時間を割けます。
その結果、従来の学習法よりも能動的なアウトプットの機会を増やせます。学んだことをしっかりと定着させて、実用可能なものにブラッシュアップできるようになるのです。
管理者が進捗を管理しやすくなる
アウトプットや質疑応答などによって学習者とのコミュニケーションが増えれば、管理者は学習者の習熟度や進捗を管理しやすくなります。その結果、一人ひとりの得意や不得意を洗い出せるようになり、個別フォローを行いやすくなるのです。講師が一方的に発信する一方通行の教育ではなく、学習者と意思疎通しながら着実に理解を深められる点は大きなメリットでしょう。
反転学習のデメリット
反転学習は魅力的なメリットが多い一方、気をつけておきたいデメリットが存在するのも事実です。ここでは、注意したいデメリットについて説明します。
事前学習をこなす必要がある
反転学習では、事前学習をしないと研修のカリキュラムが理解できないケースも多いです。できるだけ、あらかじめ学習をこなすための時間を用意してもらいましょう。
業務と両立しながら学習したり課題をこなしたりすることは、ビジネスパーソンにとってハードルが高いです。時間が取れず教材をサッと流し読みする社員と、しっかりと学習してきた社員では、習熟度に大きな差が出てしまうでしょう。企業単位で事前学習へ取り組めるようにサポートしないと、高い教育効果を得るのは難しいといえます。
事前学習の教材を用意する手間がある
反転学習をする際は、研修だけではなく事前学習用の教材を用意する必要があります。そのため、従来の研修と比べると時間的・金銭的コストがかかってしまうことは否めません。
しかし近年、自社で教材を用意しなくても、eラーニングサービスが提供する既存のコンテンツを活用して学習を行うのも可能となりました。コストや手間を減らしたいのであれば、こういったサービスの活用も視野に入れるといいでしょう。
反転学習のやり方

反転学習を行う際は、以下のフローを参考に進めてみましょう。
- 研修の目的やテーマを設定する
- 課題を決定する
- 学習者に事前課題を共有する
- 集合研修でアウトプットする
- 必要に応じてフォローアップを行う
まずは目的やテーマを設定し、次に事前課題を共有します。その後は通常の研修と同様に集合研修を行い、必要に応じてフォローアップしていきます。ポイントは集合研修を講義形式ではなく、事前課題をアウトプットできるカリキュラムにすること。グループワークやロールプレイングなどを通じて、知識を実践的なレベルまで引き上げていきましょう。
反転学習のポイント
反転学習の効果を最大限にしたいのであれば、ポイントを押さえた社員教育の実施が欠かせません。ここでは、反転学習のポイントを3つ紹介します。
- 事前課題でレポートやテストを提出させる
- 事前課題に取り組みやすい環境を整える
- 研修後の目標を明確にする
事前課題でレポートやテストを提出させる
学習者の習熟度に合った研修を行うためにも、研修の前段階でレポートやテストを提出させることをオススメします。提出義務を課すとしっかり事前学習に取り組んでもらえるほか、学習者の習熟度に応じたカリキュラムが考案できるためです。
全員の習熟度が高ければアウトプットをメインに、習得できていない学習者が多そうであれば解説の時間を多めに取るなど、課題を踏まえたカリキュラムを作成していきましょう。
事前課題に取り組みやすい環境を整える
業務をこなしながら課題や学習を進めるのは、ビジネスパーソンにとって負担の大きいこと。そのため周囲の社員は、受講者が学習に取り組める環境を整えることが大切です。
また、事前学習の手段としてeラーニングを活用すれば、学習者は移動時間や空き時間などで効率よく学習できます。こういった反転学習をサポートするツールを活用することも検討してみてください。
研修後の目標を明確にする
単に知識を詰め込むだけでは、社員教育として十分とはいえません。反転学習を行う際は、「研修後に学んだ知識をどのように生かすのか」について目標を立てることが大切です。
しっかりと目標を立てたら、どれほど達成できているのかについて上司とフィードバックを行ってください。目標の設定と軌道修正を繰り返すことで、教育で身につけた知識が確実に定着していきます。
反転学習に使えるオススメツール「playse.ラーニング」
反転学習は、事前学習をして知識を深めてから集合研修などを受けることで、知識を確実に身につけていく学習方法です。社員教育との相性が非常に良好なため、なかなか研修の成果が出ないという場合はぜひ一度検討してみてください。
効果的に学べる反転学習には「事前学習の時間がかかる・教材を用意する必要がある」などのデメリットもあります。こういったデメリットを解消して効率的な研修を行えるツールが「playse.ラーニング」です。
「playse. ラーニング」は5,000を超える豊富なレッスンが月額19,800円〜(税込)の低コストで見放題のeラーニングシステムです。スマートフォンやパソコンからいつでもどこでも学習できて繰り返し学べるため、反転学習の事前学習に最適です。またテスト・アンケート機能つきなので、集合研修前の習熟度チェックにも役立ちます。
詳しいサービス資料のダウンロード、社員研修のオンライン化やeラーニングシステムの活用に関するご相談など、お気軽にお問い合わせください!